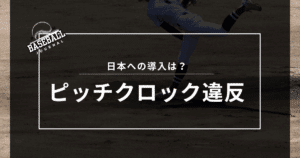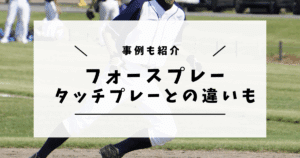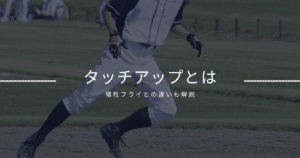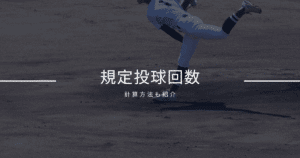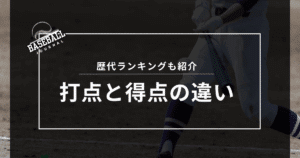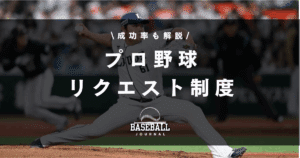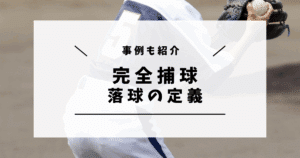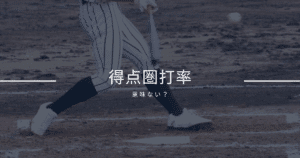野球中継で「スリーバント失敗でアウト」と耳にすることがありますが、なぜ3回目のバントが失敗するとアウトになるのか、きちんと理解できている人は意外と少ないかもしれません。
観戦中に疑問を抱いたり、子どもに説明できず困った経験がある方も多いでしょう。
この記事では、スリーバントの基本ルールやアウトになる理由をわかりやすく整理し、さらに戦術的な意味や実際の試合での使われ方まで解説します。
このページでわかること
- スリーバントの定義とルールの基本
- 3回目のバント失敗がアウトになる仕組み
- 他のバント戦術(スクイズやセーフティバントなど)との違い
- スリーバントのスコアの書き方
- プロ野球や高校野球での具体的なスリーバント事例
野球のスリーバントとは
2ストライク追い込まている状況でバントを試みることを指します。
よく3回目のバント(1ストライク、2ストライクどちらもバント失敗)と勘違いされやすいですが、2ストライク追い込まれた状態のバントであればスリーバントと表現されます。
スリーバント失敗
スリーバントは、ファールであっても三振と記録されます。そのため、ピッチャーがストライクゾーンに投球することは確実に勝負が決着する(下記参照)ことを意味します。
- 見逃し三振
- 空振り三振
- ファールで失敗
- フェアゾーンに転がる(フライ/ゴロ)
バントの種類
| 種類 | 狙い |
|---|---|
| ランナーの進塁 | 2塁や3塁などの得点圏へ進塁させることで得点の可能性をアップする狙い |
| 揺さぶり | バントの構えをすることで、投手や守備へのプレッシャーをかけます |
| セーフティ | ヒット狙いのバント(プッシュバント等も含む) |
| バスター | バントの構えで守備を前に出させてヒッティングすることで、ヒットの可能性を高める |
バントには場面に応じた上記のような様々な意図や狙いがあります。
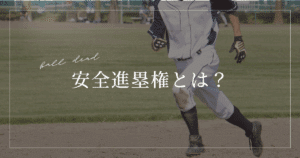
スリーバントの意味
スリーバントをする意味、メリットをご紹介します。
意表を付ける
基本的に追い込まれてからのバントはあまりありません(バントに失敗してしまい、三振となる可能性とヒッティングをしてみる可能性を比較した時に、後者はチャンス拡大の可能性も秘めています。
そのため、追い込まれてからはヒッティングに切り替える作戦を取ることがほとんどです。
それは守備側も認識していることなので、そこでバントをすることで意表を付けます。ただ「意表を付ける」だけではバントのサインは出さないでしょう。これから紹介する理由+意表を付けるといった付加価値的意味です。
進塁の重要性
どうしても、この場面は得点圏にランナーを置きたい場面や次の打者がチームの中心打者など、進塁の重要性が著しく高い場面でスリーバントを使用します。
それは、ランナー3塁の場面でも同様で、どうしても1点が欲しい場面ではスクイズを使用することもあるでしょう。
打者の打率
プロ野球ではよくありますが、打者が投手の場合はヒットを打つ可能性は低いうえに三振の可能性も高いです。
それであればより確率の高いバントを最後まで挑戦させることもあります。プロ野球ではよく、投手がスリーバント失敗する場面がありますね。
スリーバントのスコアの書き方
「K」が書き込まれます。
バントファールによる失敗の場合は「◆K」です。
成功の場合
例えば、バント成功でピッチャーが処理して1塁に送球した場合は「1-3」と表記します。その「1-3」を四角で囲むか、◇を付けることでバント成功と区別することが多いです。
スリーバントの事例とエピソード
スリーバントはルール上知られているものの、実際に試合で登場すると大きな注目を集めます。プロ野球と高校野球では使われ方が異なり、珍しい場面では思わぬドラマを生むこともあります。
プロ野球でのスリーバントの活用例
プロ野球ではスリーバントは滅多に登場しませんが、重要な場面で奇襲として選ばれることがあります。成功すれば効果的ですが、失敗すると批判の対象になりやすい戦術です。主に以下のような状況で選ばれることがあります。
- 終盤の接戦で走者を確実に進めたい場面
- 相手守備が予想外に前進していないとき
- 打者がバント技術に自信を持っているとき
このように、プロでは「ここぞ」という場面での意外性を狙った戦術として使われるのが特徴です。
高校野球でよく見られるケース

高校野球では、スリーバントは比較的よく採用されます。これは、守備の安定度に差があり、相手のエラーを誘える可能性があるためです。特に甲子園などの大舞台では、スリーバントの成否が勝敗を分けることさえあります。
| 場面 | 意図 | リスク |
|---|---|---|
| 序盤の送りバント | 確実に走者を進めたい | 三振でチャンスを潰す可能性 |
| 終盤の接戦 | 相手にプレッシャーを与える | 失敗時に流れを失う |
| 守備が不安定な相手 | エラーを誘う | バッターに精神的負担が大きい |
こうした背景から、高校野球では「スリーバント=勝負を分ける作戦」として頻繁に見られるのです。
珍プレー・名場面に見るスリーバント
スリーバントは緊迫した状況で行われるため、しばしば珍しい場面や記憶に残る名場面を生み出します。代表的な事例を整理すると次のようになります。
- 狙った以上に絶妙な転がしとなり、スリーバント成功が内野安打に変わる
- 守備側が焦って悪送球し、想定外に大量得点につながる
- 極限の緊張下で空振りし、三振でベンチも観客も一気に落胆する
このようなシーンは試合の流れを劇的に変えることもあり、スリーバントの特異性を際立たせています。成功と失敗のコントラストが強いため、珍プレーや名場面として語り継がれることが多いです。
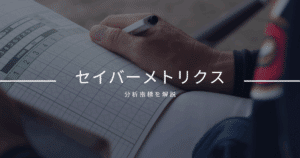
スリーバントまとめ
スリーバントとは、ツーストライク追い込まれた状態でもバントする行為を指します。
仮にファールであっても打者は三振扱いとなり、アウトとなります。どうしてもランナーを進塁させたい場面や打者の打率が低い場合などでは、作戦としてスリーバントが採用されます。
成功さえしてしまえば、ランナーの進塁可能性も高い(相手もスリーバントは全力警戒しづらいため)ですが、しっぱいしてしまえば三振で相手にアウトを1つあげてしまうだけになるため、リスクもあるプレーです。