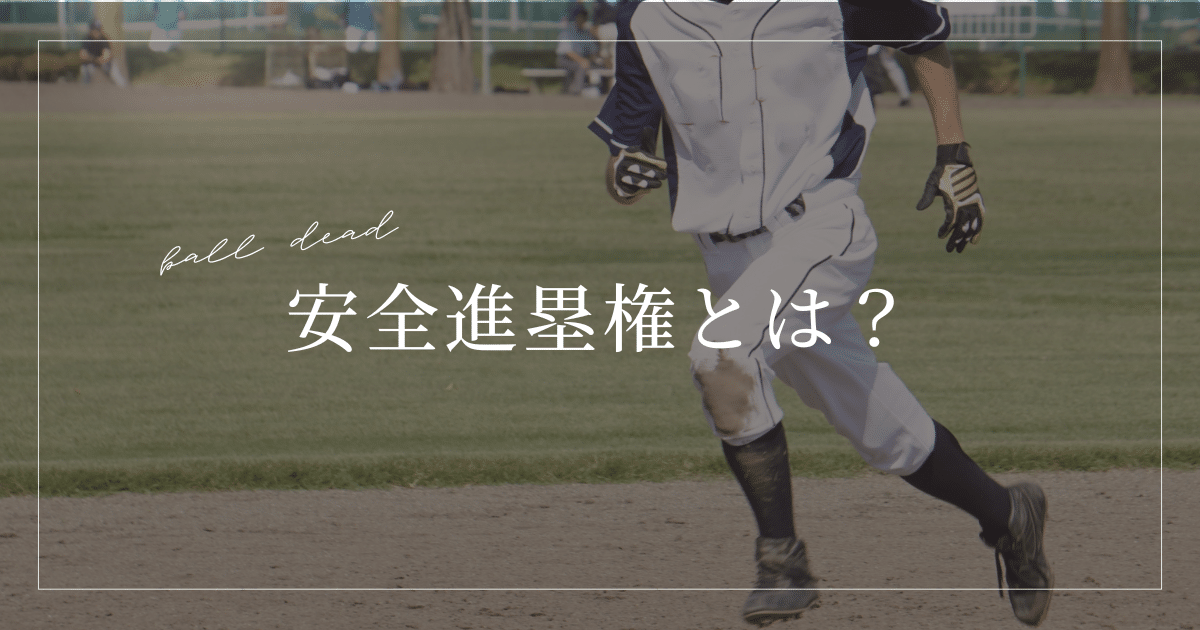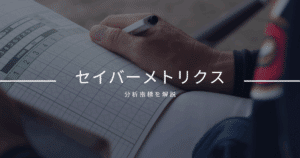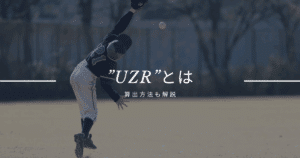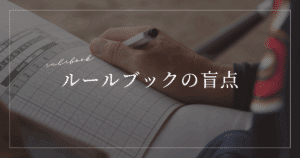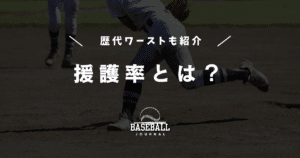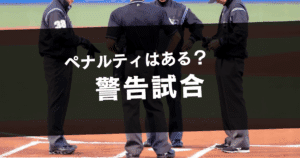野球やソフトボールの試合中、「今のプレーでランナーが進んだけど、アウトじゃないの?」と疑問に思った経験はありませんか?
それはもしかすると「安全進塁権」というルールが関係しているかもしれません。
安全進塁権は、守備側のミスなどがあった際に、走者に自動的に進塁を許す制度で、初心者にとっては理解しにくいポイントの一つです。特に子どもが野球を始めたばかりの家庭や、コーチとして審判を任されることになった方にとっては、不安や混乱の原因にもなりがちです。
そこで本記事では、「安全進塁権とは何か?」を解説します。
このページでわかること
- 安全進塁権の定義と基本的な意味
- 安全進塁権が与えられる具体的なシチュエーション
- 間違えやすいルールとの違いと注意点
- 子どもや初心者へのわかりやすい指導方法
野球の安全進塁権(ボールデッド)とは

ボールデッドとは、試合の進行が中断している状態を指します。
ボールデッドと対になる言葉がボールインプレイです。プレイボールで野球が始まると、試合は、ボールインプレイかボールデッドの状態、どちらかの状態であります。
ボールデッドの時に起こっているプレイは無効となります。そのため、ボールデッドの時には進塁などもできません。
ボールインプレイとは
ボールインプレイとは、試合が進行している、動いている状態を指します。試合中は、審判がタイムをかけるまでは、基本的にはボールインプレイの状態です。
安全進塁権とは
安全進塁権とは、字の通り、安全に進塁する権利のことを指します。
例えば、フォアボール(四球)の際はバッターはアウトにされることなく1塁に進むことができます。また、ホームランの場合も、アウトにされることなくホームインすることが可能となります。
上記のようなアウトになるリスクがなく進塁できる状態を安全進塁権と言います。
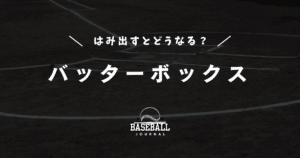
なぜ安全進塁権が存在するのか?
安全進塁権の背景には、試合を公正に進行させるための配慮があります。守備の明らかなミスにより、攻撃側が損をするような事態を避ける目的で設けられた制度です。
- 試合の公平性を守る
↳守備側の失策で攻撃側が不利にならないための配慮 - プレーの安全性を確保
↳無理な走塁や接触プレーを防ぐための措置 - 審判の判断基準を明確化
↳ミスの程度にかかわらず統一的に処理できる
特に少年野球や初心者同士の試合では、プレーの混乱を最小限に抑えるためにも重要なルールとなっています。
安全進塁権と進塁権の違い
似たような言葉に「進塁権」がありますが、安全進塁権とは明確に区別する必要があります。
| 項目 | 進塁権 | 安全進塁権 |
|---|---|---|
| 進塁の起因 | ランナーの判断・打球の結果 | 守備側のミスや規則違反 |
| 守備との接触 | タッチアウトの可能性あり | タッチ不要で進塁できる |
| 審判の判断 | 不要 | 審判が指示する進塁 |
進塁権は攻撃側のアグレッシブな判断に基づくものであり、安全進塁権は守備の失策に対する保護措置です。混同しやすい概念ですが、両者の違いを理解することで、審判の判断やプレーの流れを正しく読み取ることができます。
野球の安全進塁権(ボールデッド)の条件

- 審判によってタイムがかけられた時
- デッドボールの時
- ホームランの時
- ファウルボールがキャッチャーに捕られなかった時(自打球も含める)
- 打球、投球、送球が観客席やダッグアウトなどのプレイングフィールド外に出た時
- フライを捕った後に、野手がプレイングフィールド外に足を踏み入れた時
- 打撃妨害が起こった時ボークの塁妨害が起こった時
- 守備妨害が起こった時
- ボールが、球審やキャッチャーのマスク、フェンスなどの隙間に挟まった時
- 反則打球の時
- 故意落球が宣告された時
- ホームスチールのランナーに投球が当たった時
- インフィールドフライの打球が捕られずに、ランナーに触れた時
上記のような場合に「ボールデッド」となります。スコアの書き方も含め、1つ1つ見ていきましょう。
審判によってタイムがかけられた時
審判がタイムと宣告するとボールデッドです。
例えば、選手や監督などがタイムを要求した際に、審判はタイムを宣告します。審判がタイムと宣告するまではボールインプレイの状態です。スコアでは表記しません。
デッドボールの時
デッドボールの時はボールデッドとなり、安全進塁権も与えられます。スコアでは、DBと記載します。
ホームランの時
ホームランの時もデッドボールの時と同様に、ボールデッドです。
そして4つの安全進塁権も与えられます。スコアでは、ひし形を書いて、ホームランが入った方向のポジションを数字(レフト→7、センター→8、ライト→9)で表します。
そして、ホームランの当たりがライナーだったら「ー」、フライだったら「⌒」と数字の上に書きます。
ファウルボールがキャッチャーに捕られなかった時(自打球も含める)
そのままファール扱いになります。
スコアでは、バントファールだと「〜」、それ以外のファールは「ー」と表します。打球、投球、送球が観客席やダッグアウトなどのプレイングフィールド外に出た時
ボールが観客席やダッグアウトに入った時もボールデッドです。また、送球がベンチなどに入った場合は、ボールデッドかつ1つの安全進塁が認められます。スコアでは、※などの記号を記入し、余白にどのような状況だったのかを文章などで記載します。
フライを捕った後に、野手がプレイングフィールド外に足を踏み入れた時
フライを捕っているため、バッターはアウトとなります。
しかし、ランナーがいる場合には次の塁への安全進塁権が与えられます。スコアでは、※などの記号を記入し、余白にどのような状況だったのかを文章などで記載します。
打撃妨害が起こった時
キャッチャーがバッターの打撃を妨害すると打撃妨害です。
スコアでは、打撃妨害のことをIF(インターフェア)と表します。打撃妨害をするのはキャッチャーなので、「2IF」と記録します。
ボークの時
ボークの時もボールデッドです。ランナーがいる場合は、それぞれに1つずつ安全進塁権が与えられます。スコアでは、BKと表します。
走塁妨害が起こった時
ランナーが野手に走塁を妨害された時のことを走塁妨害といいます。スコアでは、OB(オブストラクション)と表します。
誰が走塁妨害をしたのかを記すため、例えばセカンドが走塁妨害をした場合は「OB4」と記載します。
守備妨害が起こった時
守備をしようとした野手を遮るようなことをするのが守備妨害です。
スコアでは、IFとも、IPともどちらでも表します。打撃妨害のIFと見分けをつけるために、IPとすることがあります。
ボールが、球審やキャッチャーのマスク、フェンスなどの隙間に挟まった時
ランナーがいないときは、ストライクはストライク、ボールはボールとそのままの判定です。
しかし、ランナーがいる場合には、ランナーに対して安全走塁権が与えられます。スコアでは、※などの記号を記入し、余白にどのような状況だったのかを文章などで記載します。
反則打球の時
打者が片足を打席の外に置いて打った場合に、反則打球となります。スコアでは、※などの記号を記入し、余白に反則打球と書きます。
故意落球が宣告された時
打球が内野フライだった時に、内野手がボールに触れた後に意図的に落とすことが故意落球です。スコアでは、※などの記号をつけてプレイの詳細を文章で表します。
ホームスチールのランナーに投球が当たった時
記録ではホームスチールで生還とそのままの判定となります。
スコアでは、記録はボール扱いになるため、ランナーにはスチール(盗塁)の「S」で表します。バッターはボールなので「・」と表します。
インフィールドフライの打球が捕られずに、ランナーに触れた時
インフィールドフライが宣告されたときに、ランナーが塁から離れていたらバッターもランナーもアウトになります。
塁についていて打球に触れた場合は、バッターのみアウトとなります。スコアでは、※などの記号を記入し、余白にどのような状況だったのかを文章などで記載します。

野球の安全進塁権(ボールデッド)の間違えやすいケース
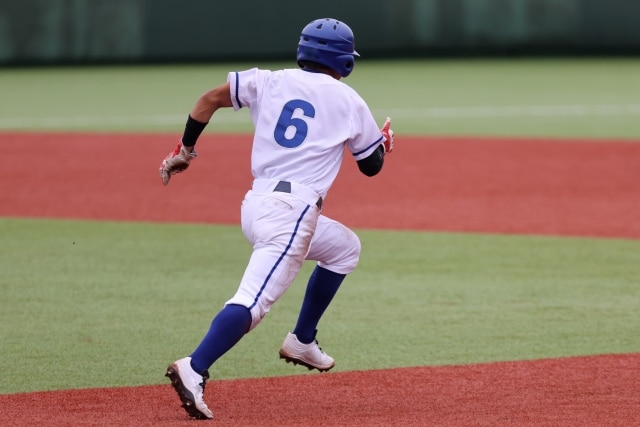
安全進塁権は、他のルールと見た目が似ているため混乱を招きやすく、試合中のトラブルの原因にもなります。
インフィールドフライや守備妨害との混同
インフィールドフライや守備妨害と安全進塁権は、プレー状況が似て見えるため、判断を誤りやすいポイントです。違いを明確にするため、下表に整理します。
| ルール名 | 発生条件 | 主な判断基準 | 走者の扱い |
|---|---|---|---|
| インフィールドフライ | 無死または一死・ランナー1・2塁または満塁 | 内野で容易に捕球可能なフライ | 打者は自動アウト、走者は進塁可能だがリスクあり |
| 守備妨害 | 攻撃側が守備の動作を妨げた | 接触・進路妨害・大声など | 妨害と判断されればアウトや走者戻し |
| 安全進塁権 | 守備のミスや規則違反が発生 | ボールがデッドゾーンへ、悪送球など | 走者は自動で進塁、タッチ不要 |
このように、適用条件や処理の仕方が大きく異なるため、プレーの経過と審判の判断に注目することが重要です。
審判のサインやジェスチャーの理解
安全進塁権の判定時、審判は明確なサインでその意図を示します。選手やベンチがそれを見落とすと混乱が生まれるため、基本的なジェスチャーは覚えておきましょう。
- 片手で次の塁を大きく指す
↳どの方向へ進塁が許可されているかを明示 - 「タイム!」のポーズのあと進塁指示
↳デッドボールやボールデッド後の処理でよく使われる - 「セーフ」のジェスチャーを繰り返す
↳ランナーが自由に進めることを知らせる
審判の動きはプレーの一部として理解し、指導の場でも再現練習をすることで、混乱を未然に防げます。
試合中に起きやすい混乱事例
実際の試合では、安全進塁権の扱いで次のような誤解やトラブルが発生しやすくなります。
| 状況 | 混乱の原因 | 結果 |
|---|---|---|
| 悪送球がスタンドイン | 進塁が許されるか不明でプレーが中断 | 審判が明確な指示を出さず、監督同士が抗議 |
| ダブルプレー狙いで暴投 | 走者が勝手に進塁し審判と見解が食い違う | 審判はすでに2個進塁を認めていたが伝わらず |
| 審判のサインが小さすぎて見えない | ベンチが進塁の理由を把握できず抗議 | プレー後に説明が必要となり試合が中断 |
こうした混乱を防ぐには、審判側がサインをはっきり出すことと、選手やベンチがルールの基本を理解しておくことが不可欠です。
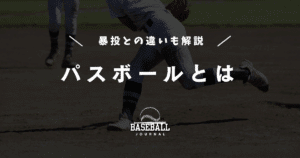
まとめ|安全進塁権を理解して正しい判断を
この記事では、「安全進塁権とは何か?」という基本から、具体的な適用場面、混乱しやすいケースまで幅広く解説してきました。
守備側のミスやルール違反により、走者がタッチ不要で進塁できるという点は、通常のプレーとは大きく異なります。また、インフィールドフライや守備妨害など類似したルールと混同されやすいため、違いを明確に理解することが必要です。
特に試合中の混乱を避けるためには、審判のジェスチャーや進塁の根拠を選手やベンチが把握しておくことが重要です。そして、指導者や保護者としては、子どもたちにもわかりやすく伝える工夫が求められます。
実際のプレーにおいては、ルールそのものだけでなく、「なぜそのルールがあるのか」という背景理解が冷静な判断につながります。この記事を通じて得た知識を、試合や練習の現場で活かし、よりスムーズで公正なゲーム運営に役立ててください。