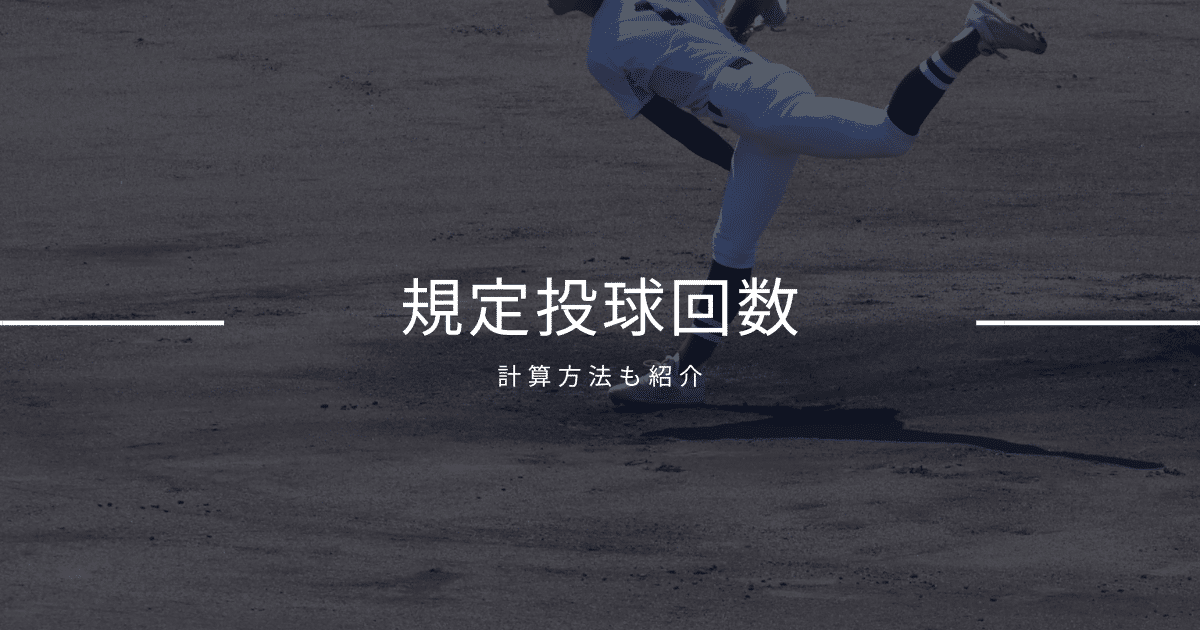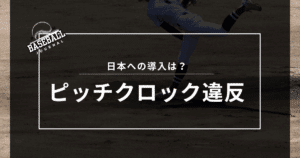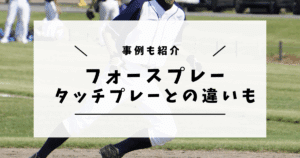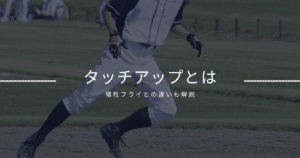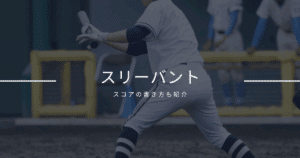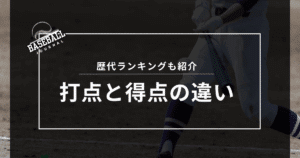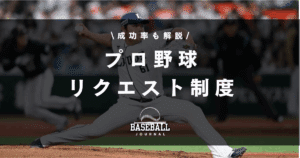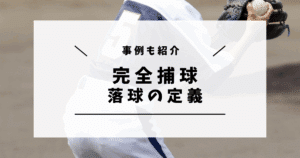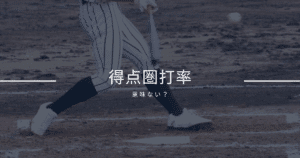プロ野球の試合を見ていると「規定投球回数」という言葉を耳にすることがありますが、その意味を正しく理解している方は意外と少ないかもしれません。
成績表やニュースでよく見るこの用語は、投手の実力を評価するうえで非常に重要な基準のひとつです。特に防御率ランキングや各種タイトル争いにおいては、この「規定」に達しているかどうかで扱いが大きく変わってきます。
この記事では、プロ野球における「規定投球回数」とは何か、どのような基準で決まるのか、そしてそれがなぜ重要なのかを初心者にもわかりやすく解説します。
このページでわかること
- プロ野球における「規定投球回数」の正確な意味と基準
- 防御率などのタイトルと規定回数の関係性
- 先発投手と中継ぎ投手で達成の難易度が異なる理由
- 過去に規定未達で惜しくもタイトルを逃した選手の事例
- 他の規定(規定打席など)との違いと成績表の読み解き方
規定投球回数とは

規定投球回数:最優秀防御率のタイトルを獲得する際に必要な投球回のこと
そもそも防御率は投球回数と自責点を計算で利用します。そのため、母数の投球回数が極点に少ないと、防御率が良い成績になることは必然です。
そのため、一定の基準を設けない限りタイトルの公平性が失われます。そこで、規定投球回数を設けることでタイトルに公平性を持たせました。
基本的には、シーズンローテーションを守った投手のみが規定投球回数に到達します。
規定投球回数の定義と計算方法
「規定投球回数」は、所属チームの試合数と同じ回数以上のイニングを投げることで達成となります。基本的なルールは以下の通りです。
- 1試合=1回分としてカウント
↳シーズンの試合数がそのまま必要な投球回数になる - 0.1回単位で記録される
↳三者凡退で1.0回、1アウトで0.1回として計算される - 先発投手向けの指標
↳ローテーションを守って登板することで到達可能な基準
たとえば、ペナントレースが143試合制であれば、規定投球回数も143回となります。以下に試合数と必要投球回数の関係を表で整理しました。
| シーズン試合数 | 規定投球回数 |
|---|---|
| 143試合 | 143回 |
| 140試合 | 140回 |
| 120試合(短縮シーズン) | 120回 |
このように、毎年の試合数に応じて、規定回数も変動します。
先発と中継ぎで違う達成の難しさ
規定投球回数は、実質的には「先発投手」のための基準です。中継ぎや抑え投手が達成するのは極めて困難であることを理解する必要があります。
以下に、各ポジションの平均的な投球回数を比較した表を用意しました。
| ポジション | 1登板あたりの平均投球回 | 規定回数到達に必要な登板数(143回の場合) |
|---|---|---|
| 先発投手 | 5~7回 | 約20~29登板 |
| 中継ぎ投手 | 1~2回 | 約72~143登板 |
| 抑え投手 | 0.2~1回 | 143回でも難しい |
このように、中継ぎや抑えでは試合に多く出場しても1試合あたりの投球回が少ないため、規定投球回数に達するのは現実的ではありません。そのため、彼らの成績がランキングに載らない理由を知っておくと、評価の見方がより深まります。
規定投球回数達成が難しい理由

規定投球回数の達成が難しい理由について解説します。
投球ペース
先発投手が6人いると仮定した場合、143÷6=23.8…となります。つまり、年間で約24試合の登板です。
24試合で143回の規定投球回を超えるためには1試合あたり、6イニング必要です。
6イニングを毎回投げるためには、試合を作れている前提になるため、毎試合QSのような登板が必要になります。QSとは、6回3失点以内に抑える先発投手の指標です。
このQS率は大エースでも中々100%になりません。つまり、この規定投球回をクリアするのは単純計算でも難しい基準となっております。
戦い方の変化
近年の野球は継投前提です。
- 先発
- 中継ぎ(セットアッパー)
- 抑え(クローザー)
といった役割分担が明確にされています。仮に完封ペースでも相性や試合展開によっては降板させられることが多いのが近代野球です。そのため、昔に比べると規定投球回の達成が難しくなっています。
中5~6日
近代野球では「怪我」への考慮が最大限されます。怪我をしないために、十分な休養をなるべくとるという文化が年々強くなっております。
そのため、中5日以上は絶対。中6日は必要といった声がファンからも多くなりました。
ジャイアンツが中4日ローテーションを組んだ際、シーズン終盤まで持たないといったファンからの非難が非常に多かったですが、事実シーズン終盤のジャイアンツ投手陣はボロボロでした。
規定投球回達成者【過去3年】
過去3年の規定投球回達成者について紹介します。
2020年
【セ・リーグ】
- 大野雄大
- 森下暢仁
- 菅野智之
- 西勇輝
- 九里亜蓮
- 青柳晃洋
【パ・リーグ】
- 千賀滉大
- 山本由伸
- 有原航平
- 涌井秀章
- 高橋光成
- 美馬学
- 田嶋大樹
- 石川歩
セ・リーグ6名、パリーグ8名の計14名が達成しました。
2021年
【セ・リーグ】
- 柳裕也
- 青柳晃洋
- 大野雄大
- 森下暢仁
- 大瀬良大地
- 小笠原慎之介
- 西勇輝
- 九里亜蓮
- 戸郷翔征
【パ・リーグ】
- 山本由伸
- 宮城大弥
- 上沢直之
- 伊藤大海
- 田中将大
- 則本昂大
- 今井達也
- 石川柊太
- 加藤貴之
- 岸孝之
- 田嶋大樹
- 小島和哉
- 髙橋光成
- 松本航
セ・リーグ9名、パリーグ14名の計23名が達成しました。
2022年
【セ・リーグ】
- 青柳晃洋
- 西勇輝
- 今永昇太
- 大野雄大
- 戸郷翔征
- 小笠原慎之介
- 小川泰弘
- 菅野智之
- 森下暢仁
- 柳裕也
【パ・リーグ】
- 山本由伸
- 千賀滉大
- 加藤貴之
- 高橋光成
- 伊藤大海
- 小島和哉
- 宮城大弥
- 田中将大
- 上沢直之
セ・リーグ10名、パリーグ9名の計19名が達成しました。
2023年
【セ・リーグ】
- 九里 亜蓮
- 東 克樹
- 戸郷 翔征
- 小笠原 慎之介
- 柳 裕也
- 床田 寛樹
- 山﨑 伊織
- 今永 昇太
- 伊藤 将司
- 髙橋 宏斗
- 村上 頌樹
- 小川 泰弘
【パ・リーグ】
- 上沢 直之
- 山本 由伸
- 加藤 貴之
- 小島 和哉
- 髙橋 光成
- 則本 昂大
- 伊藤 大海
- 平良 海馬
- 宮城 大弥
- 田中 将大
セ・リーグ12名、パリーグ10名の計22名が達成しました。
2024年
【セ・リーグ】
- 東 克樹
- 戸郷 翔征
- 才木 浩人
- 床田 寛樹
- 菅野 智之
- 大瀬良 大地
- 村上 頌樹
- 森下 暢仁
- 山﨑 伊織
- 大竹 耕太郎
- 小笠原 慎之介
- 髙橋 宏斗
- ジャクソン
【パ・リーグ】
- モイネロ
- 武内 夏暉
- 今井 達也
- 有原 航平
- 早川 隆久
- 伊藤 大海
- 加藤 貴之
- 隅田 知一郎
- 岸 孝之
- 種市 篤暉
- 山﨑 福也
- 小島 和哉
セ・リーグ13名、パリーグ12名の計25名が達成しました。
規定投球回数に関する豆知識と過去の事例
規定投球回数は単なる成績評価の基準にとどまらず、過去にはドラマティックな出来事や選手の名場面にも関わってきました。ここでは、惜しくも達成できなかった事例や、シーズンごとの投球回数の変遷、さらには未到達ながら高い評価を得た選手の実力について紹介します。
あと1回足りずにタイトルを逃した例
規定投球回数をわずかに下回ったことで、タイトルを逃してしまった選手は少なくありません。代表的な例を以下にまとめます。
- ダルビッシュ有(2005年・日本ハム)
↳142回を投げながら、あと1回届かず防御率1位に非掲載 - 前田健太(2011年・広島)
↳怪我による登板回避で規定未達。防御率は1点台だったが対象外 - 石川雅規(2007年・ヤクルト)
↳登板数は多かったが、リリーフ登板もあり回数不足
たった「1回」の不足でタイトルから外れてしまう現実は、数字の厳しさとプロ野球の世界のシビアさを物語っています。ファンにとっては悔しさと同時に、その努力と実力を記憶に刻むきっかけにもなります。
過去のシーズンごとの投球回数と試合数の推移
プロ野球のシーズン試合数は時代や特別事情により変動しており、それに伴って規定投球回数の基準も変わってきました。以下に代表的なシーズンのデータを整理しました。
| シーズン | 試合数 | 規定投球回数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 120試合 | 120回 | 新型コロナによる短縮シーズン |
| 2021年〜現在 | 143試合 | 143回 | 通常シーズン |
| 1990年代 | 130〜135試合 | 130〜135回 | 年によって変動 |
このように、規定投球回数は固定された数字ではなく、毎年の試合数に連動して設定されるものです。したがって「143回」が常に基準とは限らず、過去の成績を比較する際はその年の試合数も確認することが重要です。
未到達でも注目される投手の実力
規定投球回数に達していないからといって、評価されないわけではありません。特に中継ぎや抑え投手などは、回数の少なさに対して非常に高いパフォーマンスを発揮している選手も多く存在します。
代表的な例を見てみましょう。
- 藤川球児(全盛期)
↳規定投球回に未到達ながら、シーズン防御率0点台で圧巻の活躍 - 佐々木朗希(2022年)
↳登板数が限られていたが、完全試合達成などで注目を集める - クローザー型外国人投手(例:デニス・サファテ)
↳1試合あたりのインパクトが大きく、年間通じて安定した成績
彼らは規定に届いていなくても、チームの勝敗に直結するような重要な場面での活躍が評価され、多くのファンに記憶されています。成績表だけでは伝わらない「存在感」も、野球を語るうえで大切な視点です。
野球の規定投球回数まとめ
規定投球回数:防御率のタイトルを獲得する際の対象選手を決めるための指標
継投文化の確立や中5日以上が主流になってきた現代野球において、規定投球回数の達成難易度はあがっております。基本的に1年間を通してローテーションを守った投手しかクリアすることができません。
近年では、良い投手でも怪我の離脱によって防御率のタイトル対象者にならないような選手も多いです。
規定投球回数を下げるべきの声もありますが、やはり1年間ローテーションを守った選手を対象にできているため、個人的に規定投球回数の計算を変える必要はないと思っております。