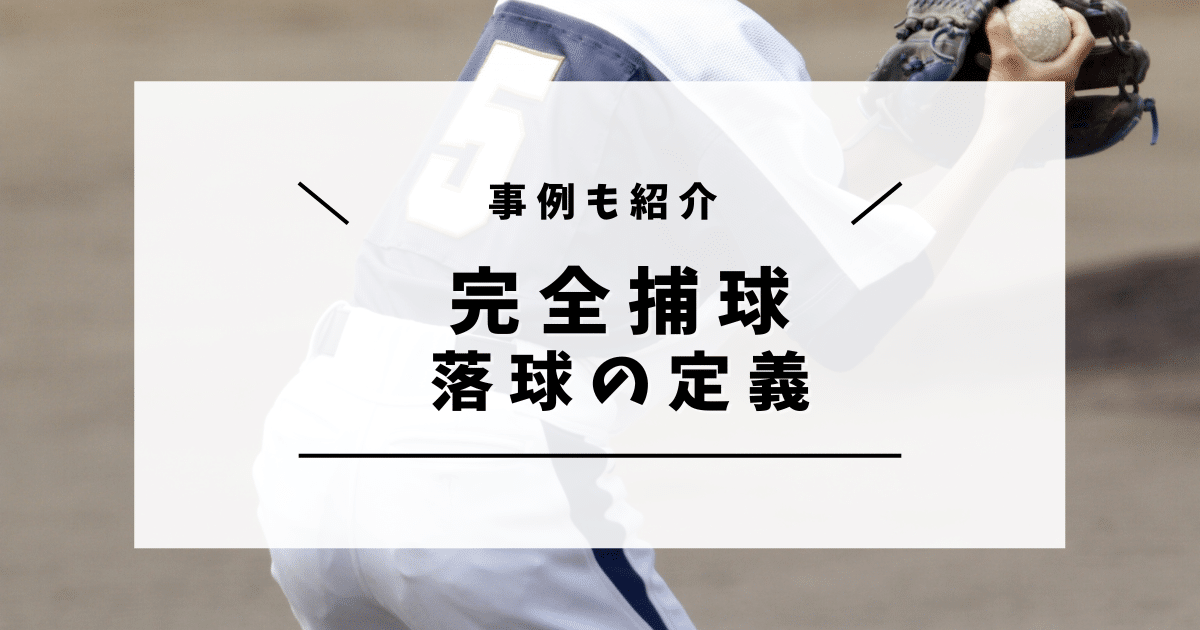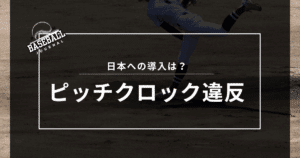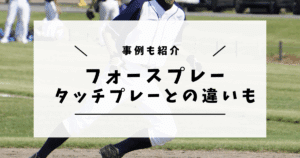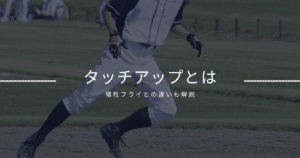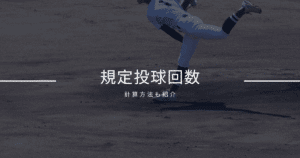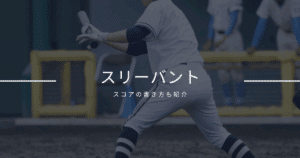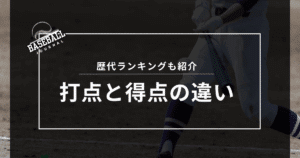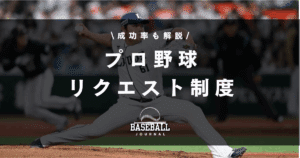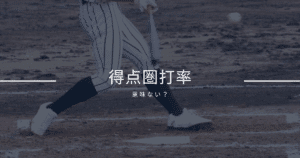野球の完全捕球とは、一度ボールを確実にキャッチすることを指します。
つまり、グローブに収まりきった場合は完全捕球となります。そのため、キャッチから投げるまでの握り替えの動作の際にボールを落としても、キャッチしてグローブのなかに収まった時点で完全捕球は成立しています。
そこで本記事では、完全捕球の定義と実際に捕球関連で物議を醸した事例を紹介していきます。
完全捕球とは

完全捕球とは、ボールを確実にキャッチしたと判定されることを指します。
キャッチ後の送球に握り替える際にボールを落としてしまった場合も、一度キャッチが完了していれば完全捕球として認められます。
明確に〇秒の静止といった判定基準はないため、審判判断に委ねられることも少なくありません。
野球規則
野手がボールを受け止めた後、これに続く送球動作に移ってからボールを落とした場合は、〝捕球〟と判定される。要するに、野手がボールを手にした後、ボールを確実につかみ、かつ意識してボールを手放したことが明らかであれば、これを落とした場合でも〝捕球〟と判定される。
出典:公認野球規則
つまり、一度ボールをキャッチ(掴む)していれば完全捕球として認められます
ダイビングキャッチからの送球やファーストのショートバウンドキャッチなどといったプレーでは、完全捕球されているかどうかをそれぞれの審判が判断する必要があります。

落球の定義
落球:一度キャッチしかけたボールを落とすことを意味します。
例えばライナーを守備チームが落球した場合、打者はまだ生きています。しかし、仮にランナーが1塁にいた場合は2塁への進塁義務が発生するため、すぐに走り出す必要があります。
上記のようなルールを逆手にとり、あえて落としてダブルプレーを狙うなどの頭脳派プレイがありますが、故意落球が適用された場合は無効になります。
しかし、故意落球の線引きも審判による判断になるため、意図的に落球したのかはたまた実力かといった判断基準が非常に難しいプレーとなっています。
完全捕球の判定に迷うプレー事例と解説
完全捕球は「確実に保持しているか」「その保持がプレーの勢いに耐えているか」が鍵になります。曖昧になりやすい典型場面を取り上げ、アウトかノーキャッチかを整理します。
グラブに入ったがこぼれたケース
グラブに“入ったように見える”瞬間はしばしばありますが、完全捕球と判定されるには、その後もしっかり制御し続けている必要があります。代表的な分岐を表で整理します。
| 状況 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| フライをグラブに収め、歩数を取り静止後に持ち替えで落球 | アウト成立(プレー続行) | 保持が確認でき、転送過程での落球は捕球成立後の出来事 |
| 捕球直後、着地衝撃でボールがこぼれる | ノーキャッチ | 勢いに耐えるまで保持できておらず、完全捕球に達していない |
| グラブに触れたが即座に地面へ落下 | ノーキャッチ | 制御の確認ができないため、捕ったとは扱わない |
| グラブで一度挟み、身体に当ててから再度掴み取り | アウト(条件を満たせば) | 地面に触れておらず、最終的に確実な保持があるため有効 |
ポイントは「保持の連続性」です。衝突や着地でこぼれた場合は、保持が継続していないとみなされやすく、ノーキャッチとなります。
フェンス際やジャンピングキャッチの判定
フェンス際や観客の近くでは、接触や勢いの影響が大きく、判定が難しくなります。注目すべき観点を箇条書きで押さえましょう。
- 地面接触の有無
↳ボールが地面に触れたらノーキャッチ。グラブ内で圧しつけただけも無効になる場合あり - 勢いに耐えた保持
↳フェンス衝突や着地後まで制御が続いているかが判断材料 - 観客との接触(干渉)
↳観客がボールや野手に触れた場合は干渉の可能性。ボールデッドやアウトの可否は状況依存 - フィールド内外の位置関係
↳フィールド内で保持が完了していれば有効。越境後の落球はノーキャッチになりやすい - 送球への移行時の扱い
↳キャッチ確定後の持ち替えで落としても捕球自体は有効。走者はインプレーで進塁可
衝突や観客干渉が絡むと、見た目の派手さと判定が一致しないことがあります。最終的に「地面に触れず、勢いに負けずに制御していたか」を軸に考えると理解しやすくなります。
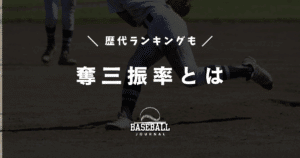
ダブルプレーでの捕球判定の重要性
併殺では、最初のアウトが成立しているかどうかで全体の結果が大きく変わります。ベース踏みと保持のタイミング、持ち替え時の落球が分岐点です。
| 二塁付近のプレー | 判定 | 解説 |
|---|---|---|
| 遊撃手が送球をしっかり保持し、二塁を踏んでから一塁へ送球 | 一つ目のアウト成立 | 保持と踏み替えが完了。以降の送球結果に関わらず最初のアウトは取り消されない |
| 送球を受けた直後にベースを踏む前にこぼす | アウト不成立 | 保持が確認できず、フォースアウトの条件を満たさない |
| 二塁を踏んだ直後、持ち替えで落球 | 一つ目のアウトは成立 | 踏みと保持が先に完了していれば、転送中の落球は最初のアウトに影響しない |
| 足だけベースに触れ、ボールは未保持のまま | アウト不成立 | 踏む動作と保持はセットで必要。順序や同期が重要 |
併殺での要は「踏む・保持・次動作」の順序です。最初のアウトが認められるかで走者配置が一変するため、内野手はベースワークと持ち替え動作の精度を揃えておくと判断が安定します。
完全捕球が絡んだプレーの事例
実際に完全捕球が絡んだプレーの事例を紹介していきます。
内野フライ
こちらのプレーはスローでみると一度グローブのなかにボールが収まっているため、完全捕球です。
リクエストが導入された現在では、判定が覆る可能性が高いですが、当時は審判が絶対になるため、ちょっと不運なプレーでした。このようにかなり審判の判断に依存するのが完全捕球関連のプレーです。
接触プレー
接触後にボールを落球してしまったこのプレー。
ビデオ判定もされましたが、完全捕球かどうかを判定するのは難しいです。
この場合(ビデオ映像でも判断が難しい場合)リクエスト前の判定が有効になります。
フェンス際
フェンスの方が先にボールに触れてるとして、判定はファールになりました。
外野フェンスでも同様のケースになることがあり、完全捕球でアウトと判定されても、フェンスに先にあたっていたとしてヒット扱いになるケースもあります。
上記の場合も完全捕球か否かが判定を分ける観点です。
完全捕球まとめ
完全捕球とは、ボールを確実にキャッチしたと判定されることを指します。
- 通常のフライ
- 選手同士の交錯
- フェンス際のプレイ
上記のようなケースで完全捕球か否かの判定がされることが多く、試合の流れを大きく変えるプレーです。握り替えの際の落球は問題ないですが、グローブのなかに収まる必要性はある。リクエスト制度でカメラ判定がある現代でもここの判断の線引きは難しいです。