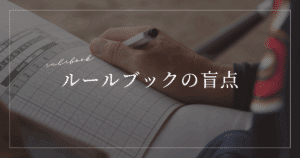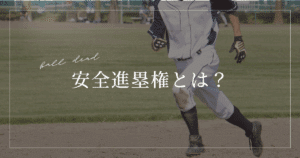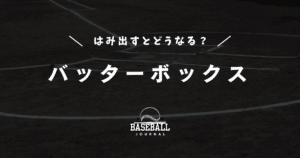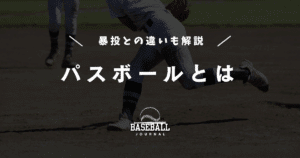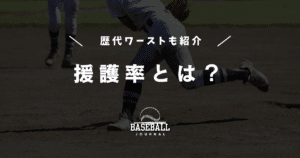野球には同じ場面であってもその過程によって表現(言葉)が変わる場合があります。例えば、アウトはアウトでもフォースアウトなのか、タッチプレーによるアウトなのかなどです。
上記と同じ理論で多くの方が疑問に思うのが「刺殺」と「捕殺」になります。
そこで本記事では、両者の違いについて解説します。ちなみにフォースアウトとタッチプレーの違いは下記記事で解説しているため、併せてご参考ください。
刺殺と補殺を理解する上で重要な守備率についても紹介しているため、是非最後まで記事をご覧ください。
このページでわかること
- 守備率とは何か?どんな意味があるのか
- 守備率の具体的な計算方法と公式
- 守備率だけでは評価しきれないポイントとその理由
- 他の守備指標(UZR・DRS)との違い
- 守備率を野球観戦で活かすための考え方
野球の守備率とは

守備機会に対して、どれだけエラー(失策)をしなかったの割合になります。
守備率が10割であれば、そのプレイヤーはエラーを1つもしていないことになります。しかし、守備機会が少なければそれだけ守備率が10割となる可能性も高まります。
つまり、母数の重要性を理解した上で、本指標を見ることでその選手の守備の実力を定量的に計ることができます。
計算方法
守備率=(刺殺数+補殺数)÷守備機会数
| 項目 | 回答 |
|---|---|
| 刺殺数 | アウトに際して最後にボールに触れたプレイヤー |
| 補殺数 | アウトに関連したプレイヤーすべて →刺殺で記録されるプレイヤーは除く |
| 守備機会数 | プレイヤーが守備に関わった回数 |
刺殺と補殺については記事下部で改めて解説します。
アウトに関わるプレーが10回あった場合、守備機会数は10となります。
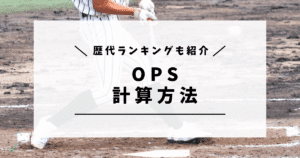
野球の刺殺と補殺の違い
| 項目 | 回答 |
|---|---|
| 刺殺 | アウトにした際に最後にボールに触ったプレイヤー |
| 補殺 | アウトにするまでに関わったプレイヤー |
刺殺と補殺は、上記のような違いがあります。
例えばショートゴロの場合、最後のボールに触れるのはファーストになります。そのため、刺殺をファーストに記録。補殺をショートに記録します。
ケース① タッチアップアウト
- センターフライ
- ショートが中継
- ホームでタッチアウト
上記の場合、センターとショートとキャッチャーの3名がボールに触れてアウトのプレーに繋がっています。
最後に触れたポジションがキャッチャーになるため、キャッチャーに刺殺が記録され、センターとショートには補殺が記録されます。
ケース② ダブルプレー
- ショートゴロ
- セカンドアウト
- ファーストアウト
上記も場合、ショートとセカンドとファーストの3名がボールに触れてアウトに繋がっています。
最後に触れたポジションがファーストになるため、ファーストに刺殺が記録されます。このようにファーストやキャッチャーなどの最後にボールを触れてアウトにする確率が高いポジションは刺殺の記録数が多くなります。
ケース③ 牽制アウト
牽制でアウトになった場合、そのタッチアウトの際のポジションに刺殺が記録されます。
守備率の意味と限界

守備率は、野球の中でもっとも基本的かつ古典的な守備評価指標の一つです。ミスの少なさを数値で確認できる点では有用ですが、守備力の全体像をとらえるには物足りなさがあるというのが実情です。
守備率で分かること、分からないこと
守備率は「守備機会に対してどれだけ確実にアウトにできたか」を表す指標です。失策の少なさ=守備の安定性を測るためには有効ですが、守備範囲の広さや反応速度などは反映されません。
この違いを明確にするため、守備率がカバーできる情報とできない情報を以下の表にまとめました。
| 守備率で分かること | 守備率では分からないこと |
|---|---|
| アウトを確実に取れるか(安定性) | 守備範囲の広さ・反応速度 |
| 失策の多さ・少なさ | 難しいプレーへの挑戦や成功率 |
| 一定の守備的信頼度 | ポジショニングや判断力 |
このように、守備率はあくまで「失策をしなかった割合」を見ているに過ぎず、それ以外のプレーの質や貢献度を測るには向いていません。
守備率が高くても守備が下手な例
守備率が高ければ、その選手は守備が上手いと考えがちですが、実際にはそうとは限りません。たとえば、守備範囲が狭い選手が「触れる範囲だけ確実に処理する」プレースタイルだった場合、失策の可能性が減るため、守備率は自然と高くなります。
しかし、そうした選手が実際には難しい打球に対応できておらず、チームの守備力に貢献できていないケースもあります。このような場合、守備率だけを見て評価すると、実態よりも高く評価されてしまう危険があります。
つまり、守備率には「挑戦しないリスクを取らない守備」が反映されにくいという盲点があることを理解しておきましょう。
ポジション別に見た守備率の違い
守備率は一見、すべてのポジションで公平に適用されるように見えますが、実際にはその見方に差があります。なぜなら、ポジションごとに守備の内容や負担が大きく異なるからです。
| ポジション | 守備率の傾向 | 理由 |
|---|---|---|
| 一塁手(ファースト) | 高く出やすい | 刺殺数が多く、比較的難易度の低いプレーが多い |
| 三塁手・遊撃手 | やや低くなりがち | 俊敏な動きが求められ、失策のリスクが高い |
| 外野手 | 非常に高く出る傾向 | 守備機会が少なく、失策の発生率が低いため |
守備率と他の守備指標との比較
守備率は野球界で長年使われてきた守備の基本的な指標ですが、近年ではそれだけでは不十分という声も多く、さまざまな新しい指標が登場しています。
とくに、守備範囲や得失点への貢献度を評価する「UZR」や「DRS」といったセイバーメトリクス系のデータが注目されています。
UZR・DRSとは?守備率との違い
UZR(Ultimate Zone Rating)とDRS(Defensive Runs Saved)は、選手の守備による得失点の影響を数値化した指標で、守備率とはまったく異なる視点から評価を行います。
それぞれの指標の特徴を整理すると以下のようになります。
| 指標 | 評価対象 | 特徴 |
|---|---|---|
| 守備率 | 失策の有無 | 伝統的な評価。安定性重視 |
| UZR | ゾーン内の守備成功率 | 守備範囲や送球、ダブルプレーなどを細かく評価 |
| DRS | 守備による得失点 | 1シーズンでどれだけ得点を防いだかを数値化 |
守備率はミスの少なさを示すのに対し、UZRやDRSはどれだけ守備で貢献できたかという「結果」や「影響度」にフォーカスしています。
守備力を多角的に見るには?
ひとつの指標だけで守備を判断するのはリスクがあります。守備率・UZR・DRSなど、それぞれの指標には得意な部分と苦手な部分があるため、複数のデータを組み合わせて見ることで、より客観的で信頼できる評価が可能になります。
- 守備率
↳確実性・安定性を見る - UZR
↳守備範囲・プレーの質を見る - DRS
↳失点・得点への貢献を見る
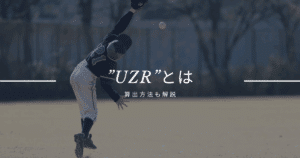
これらを補完的に使うことで、「安定しているが範囲は狭い」「失策は多いが守備範囲が広い」といった選手の特徴をより正確に掴むことができます。
セイバーメトリクスにおける守備の考え方
セイバーメトリクスでは、単なる数字の羅列ではなく「得点への影響」を重視します。そのため、守備に関しても失策数や見た目のプレーではなく、守備によってどれだけ得点を防いだか(または失点を防げなかったか)を計算し、評価の基準とします。
このような考え方に基づいて開発されたUZRやDRSは、「どのゾーンにどの打球が飛び、その中で何回アウトにできたか」を分析することで、実際の守備力を高精度に測定します。
守備率では見えてこない「守備による勝敗への貢献」を把握するために、セイバーメトリクスは非常に有効な手段です。ただし、これらの指標はデータ収集や解析に高度な技術を必要とするため、一般的な試合観戦ではあまり触れる機会が少ないのも事実です。
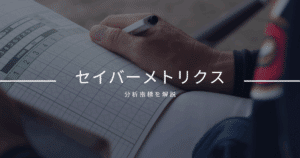
まとめ|守備率の見方を理解して、選手の本当の守備力を知ろう
この記事では、守備率の定義や計算方法から始まり、その限界や他の守備指標との違いについて詳しく解説しました。守備率は確かにミスの少なさを知る上では便利な指標ですが、それだけで守備力のすべてを評価するには不十分です。
とくに、守備範囲や得点への貢献といった側面は守備率では捉えきれないため、UZRやDRSなどのデータと組み合わせて考える視点が必要です。ポジションによる特徴や、数値の裏にあるプレースタイルの違いにも注目することで、より深い理解につながります。
守備力を評価する際には、「数字が高い=優秀」と単純に判断するのではなく、それぞれの指標の特徴を踏まえて多面的に見ることが大切です。実況や解説の中で聞こえる数字の意味をしっかり理解できるようになれば、観戦の楽しさもぐっと増します。