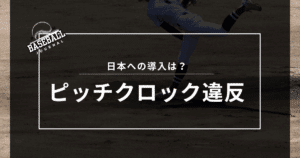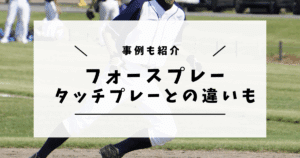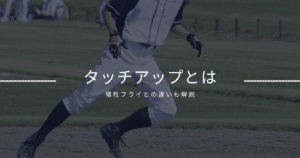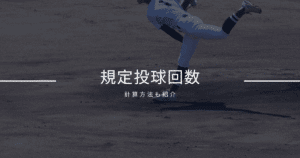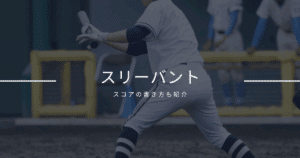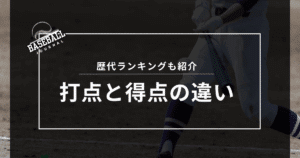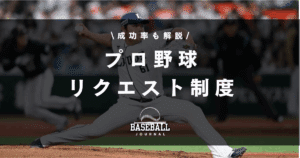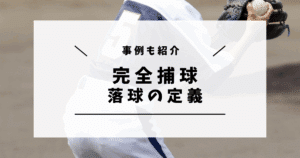セイバーメトリクスという言葉を聞いたことはあっても、その中身まで理解している人は意外と少ないかもしれません。従来の打率や打点だけでは見えてこない「本当に価値のある選手」を見抜くための考え方として、近年ますます注目を集めているのがセイバーメトリクスです。
野球が好きであればあるほど、セイバーメトリクスの考え方を知ることで、観戦や選手評価の視点が一段と広がります。しかし「数字が多くて難しそう」と感じている方も多いはず。
そこで本記事では、セイバーメトリクスの基本から、主要な指標の意味、実際の活用例までをやさしく丁寧に解説します。
このページでわかること
- セイバーメトリクスの定義とその目的
- 従来の野球指標とセイバーメトリクスの違い
- OPS、WAR、BABIPなどの主要指標の意味
- 実際の球団運営での活用例と影響
- 自分でセイバーメトリクスを使う方法
野球のセイバーメトリクスとは

セイバーメトリクス(Society American Baseball Research+metrics)とは、アメリカ野球 学会と統計学を組み合わせた造語であり、野球を数字でデータ分析し、統計学的根拠を加 えて選手の評価・戦略などを考えるといった野球における新しい手法の一つである。
https://www.osaka-gu.ac.jp/php/satoma/2013/E06/00523-miyake04.pdf
セイバーメトリクスを簡単にいうと、数字を使ったデータを基に、戦術を考える手段です。
「こういうバッター(ピッチャー)だから」といった主観にとらわれず、数字を使うことで客観的に相手を判断していく手段のことを指します。
セイバーメトリクスとは何か?その定義と目的
セイバーメトリクスは「SABR(Society for American Baseball Research)」という団体名に由来し、「野球を統計的に分析してチームの勝利にどう結びつけるかを探る学問」です。その最大の目的は、勝利に貢献する要素を客観的に評価することにあります。
従来は「打率が高い=いいバッター」と考えられてきましたが、セイバーメトリクスでは「出塁できるか」「長打が多いか」「守備や走塁の影響はどうか」など、より多角的に選手を評価します。単なる成績の羅列ではなく、勝利との相関をもとに指標を構築するのが特徴です。
このように、セイバーメトリクスは「感覚」ではなく「根拠あるデータ」に基づいて戦略を考える、新しい野球観の入口となります。
なぜ今、セイバーメトリクスが注目されているのか
セイバーメトリクスが注目される理由は、主に3つあります。1つは、球団経営の合理化に貢献できること。高額年俸のスター選手よりも、割安で貢献度の高い選手を見つけられれば、費用対効果の高いチーム作りが可能になります。
2つ目は、監督やコーチの戦術判断に具体的なデータを提供できる点です。感覚に頼らず、客観的な根拠をもとに選手起用や打順、守備位置などを決めることができます。
3つ目は、ファンの野球観戦がより深く、知的に楽しめるようになること。数字の裏にある選手の価値やチームの戦略を知ることで、試合の見方が格段に広がります。
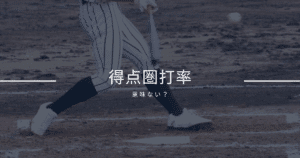
従来の指標との違いをわかりやすく解説
従来の野球指標は「結果」の数字が中心で、選手の実力を必ずしも正確に表しているとは限りません。例えば、打率はヒット数を打数で割った数値ですが、四球や死球は評価されません。一方で、セイバーメトリクスは「どうすればチームが勝つか」に直結する要素を測るのが目的です。
代表的な違いを整理すると、次の表のようになります。
| 従来の指標 | セイバーメトリクスの指標 | 評価の違い |
|---|---|---|
| 打率 | OPS | 出塁+長打を加味し、攻撃全体を評価 |
| 打点 | WAR | チームへの貢献度を総合的に測る |
| 防御率 | FIP | 守備や運の影響を除き、投手の実力を分析 |
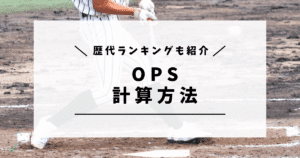
従来の指標は分かりやすく浸透してきた一方で、チームや打順、守備の影響を大きく受けるため「選手個人の力」を正しく反映していないケースがあります。セイバーメトリクスはその課題を克服し、戦術や補強方針に直結する「実戦的な分析」を可能にします。
セイバーメトリクスで用いられる指標

セイバーメトリクスで用いられる指標はかなりあります。投手、野手とわけても、かなりの量になります。そのため、この記事では代表的な下記の6つを紹介します。
- OPS
- QS
- UZR
- WHIP
- WAR
- P/PA
OPS
OPS(On-base Plus Slugging)とは、出塁率と長打率の合計値のことを表します。
出塁率と長打率が関係してきていることから、得点にどのくらい貢献できているのかを知るための指標として使われています。
得点に貢献と言えども、出塁率と長打率の合計なため、盗塁が評価されないのはOPSの欠点ともいえます。
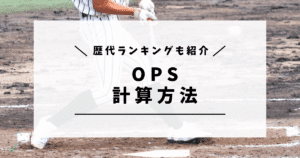
QS
QS(Quality Start)とは、先発の投手が6イニング以上投げ、自責点を3点以内で抑えた時に記録されるものです。
- 失点ではなく、自責点であることがポイント
- 7回以降に4点目の自責点を取られた場合、QSはつかない
先発投手は試合を作るために必要なポジションとなっています。
そのため、QSが記録された時は先発投手は試合を作ることができたとも判断することが可能です。

UZR
UZR(Ultimate Zone Rating)とは、守備能力の指標です。
優れた守備をした場合に評価されます。UZRについて詳しくは、こちらの記事で紹介しています。
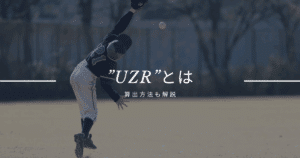
WHIP
WHIP(Walks plus Hits per Inning Pitched)とは、1イニングでどのくらいランナーを出してしまったのかという投手の指標です。
WHIP=(与四球+被安打数)÷投球回数
※死球や失策での出塁は含まれない
WHIPの数値が低ければ低いほど、投手が安定しているということが分かります。
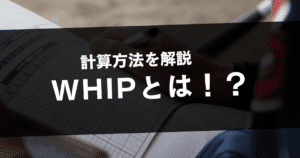
WAR
WAR(Wins Above Replacement)とは、何勝分、勝利に貢献したのかを示す指標です。
WAR=攻撃指標+走塁指標+守備指標+投手指標
WARが高ければ高いほど、勝利に貢献したということが分かります。
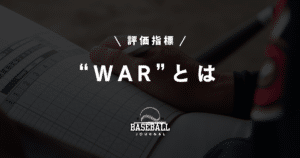
P/PA
P/PA(Pitch per Plate Appearances)とは、1打席で球数を何球投げさせたかを示す指標です。
球数を投げさせれば投げさせるほど、投手を引きずり下ろしやすくなります。
P/PA=全被投球数÷打席数
P/PAは4点を超えると高い水準になります。打者の特徴を判断するときに使えるのが、このP/PAです。
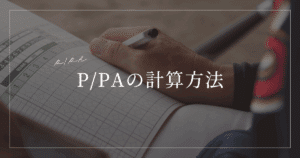
セイバーメトリクスの実用例を知ろう

理論だけでは実感が湧きにくいセイバーメトリクスですが、実際に現場で活用されている事例を知ることで、その有用性がより明確になります。特にメジャーリーグでは早くから導入され、日本のプロ野球界でも近年積極的に取り入れられ始めています。
「マネー・ボール」での活用事例
セイバーメトリクスが広く知られるきっかけとなったのが、MLBのオークランド・アスレチックスの事例です。球団のGMビリー・ビーンは、限られた予算で勝てるチームを作るために、従来のスカウティングでは見過ごされていた選手をデータ分析で発掘しました。
その際に重視されたのが「出塁率(OBP)」です。ヒットを打たなくても四球で出塁すれば得点につながるという考えに基づき、打率が低くても出塁率の高い選手を積極的に起用しました。
この戦略は2002年にチームがア・リーグ記録となる20連勝を達成するなど大成功を収め、後に映画『マネー・ボール』としても知られるようになりました。まさにセイバーメトリクスの可能性を示した象徴的な事例です。

日本プロ野球における導入例
日本でもセイバーメトリクスの概念は徐々に浸透しており、特にパ・リーグを中心に先進的な取り組みが見られます。例えば、福岡ソフトバンクホークスは独自のデータ分析部門を設け、選手の守備範囲やスイング傾向、投球の回転数まで詳細に解析しています。
また、横浜DeNAベイスターズは選手起用や練習メニューにデータを活用する体制を整え、チーム戦略に統計を積極的に反映しています。データをもとに打順やポジション変更を決定する場面も増えており、「勘」ではなく「根拠ある分析」に基づいた運営が定着しつつあります。
このような取り組みは、結果的にチーム全体のパフォーマンス向上や若手選手の育成にも良い影響を与えており、今後さらに多くの球団が取り入れると考えられます。
選手評価・補強戦略への応用
セイバーメトリクスは単に試合の戦術だけでなく、選手評価や補強の戦略においても非常に大きな役割を果たしています。たとえば、FA選手の獲得やトレードを検討する際、以下のような観点からデータ分析が行われます。
| 評価項目 | 使用される指標 | 分析の目的 |
|---|---|---|
| 攻撃力 | OPS、wOBA | 得点への貢献度を見極める |
| 守備力 | UZR、DRS | 守備範囲やプレー精度を数値化 |
| 投手の安定性 | FIP、WHIP | 防御率では見えにくい投球の質を評価 |
| 将来性 | 年齢・過去の成長曲線 | 成績の再現性や成長可能性を予測 |
このように、セイバーメトリクスは獲得候補の選定から年俸交渉、さらには戦力外通告の判断に至るまで、幅広い場面で意思決定の根拠となっています。数字を通して選手の価値を公平かつ戦略的に判断できるため、現代野球には欠かせない視点となっています。
セイバーメトリクス、野球の指標についてのまとめ
- OPS
- QS
- UZR
- WHIP
- WAR
- P/PA
本記事では、セイバーメトリクスの例として上記を紹介しましたが、あくまで一例に過ぎません。
また、セイバーメトリクスは便利なものではありますが、あくまでも統計学に基づいた結果です。セイバーメトリクスで得られた数字を見ながら野球観戦をするのも楽しいと思います。
しかし、数字に引っ張られすぎずに、目の前のプレー1つ1つに一喜一憂するのも楽しいですよ!